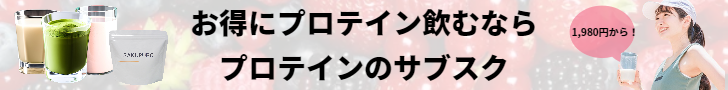湿気の影響をうけないようにする
梅雨は長雨がひたすら続き湿気が強くなりカビが生じやすくなります。この湿気がとても厄介で人体に侵入すると色々な不調をおこす「湿邪」へと変化します。
家の中では風をよび込み、風の通り道を工夫しながら湿気を飛ばして湿邪の影響を受けないようにして過ごしましょう。
湿邪の性質
・重濁(じゅうだく)
・粘滞(ねんたい)
重濁は体を重だるくさせ、粘滞は気の巡りを邪魔して脾胃の消化機能を停滞させます。不調に備えるためには湿邪の対策を施すことがスッキリ過ごすためのコツです。
![]()
香りのある食材は湿を消す
香りの強い食材には芳香化湿(ほうこうかしつ)という効能が備わり、芳香成分によって食欲を誘い、香りの力で気の巡りを促します。
![]()
そして燥湿作用により体内に溜まった余分な水分を発散させたり、流通させて取り除く働きをしてくれます。
梅雨時期の食欲不振、身体がだるい症状がすでにある時は、薬膳では芳香化湿の食材をいかして湿を消します。
湿気をのぞく香りの食材
芳香化湿の食材の使い方にはちょっとコツがあります。
梅雨どきは、梅雨寒もあれば気温が上昇する日もあり、お天気は気まぐれです。そんな自然の変化に追いつけないと体調を崩しやすくなるので、香りの食材を使い分けることで対応します。
寒さを感じる時は、温める芳香食材を使う
生姜、紫蘇、カルダモン、バジル、パクチー
暑さを感じる時は、冷ます芳香食材を使う
薄荷、セロリ、レモンバーム
体の湿気をとる香りのお茶
芳香化湿の効果を活かすには「手早く」が基本です。
薬味に使う。ハーブティーやお茶で飲む。いつもの飲み物に加える。など香りをいかした調理法がおすすめです。
![]()
食べてみる。自分の体調の変化を感じる。そんな風に薬膳の智慧をとりいれてみてください。